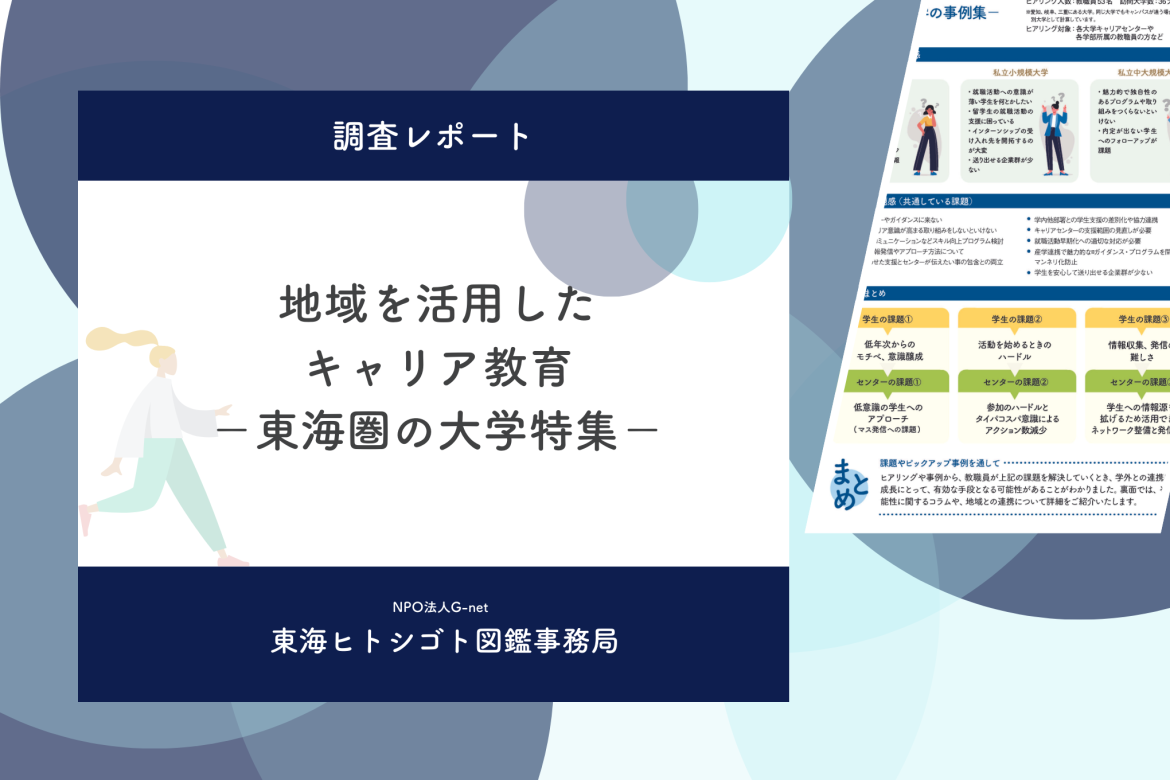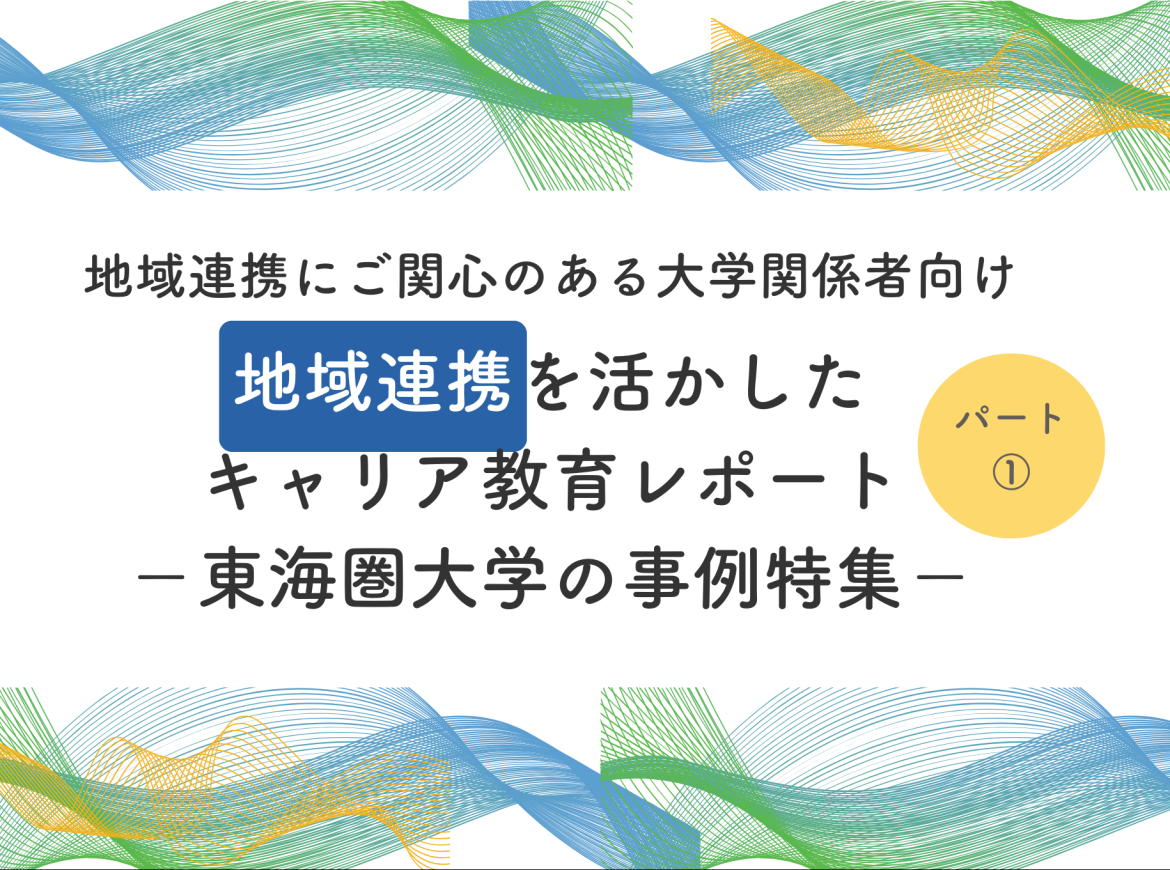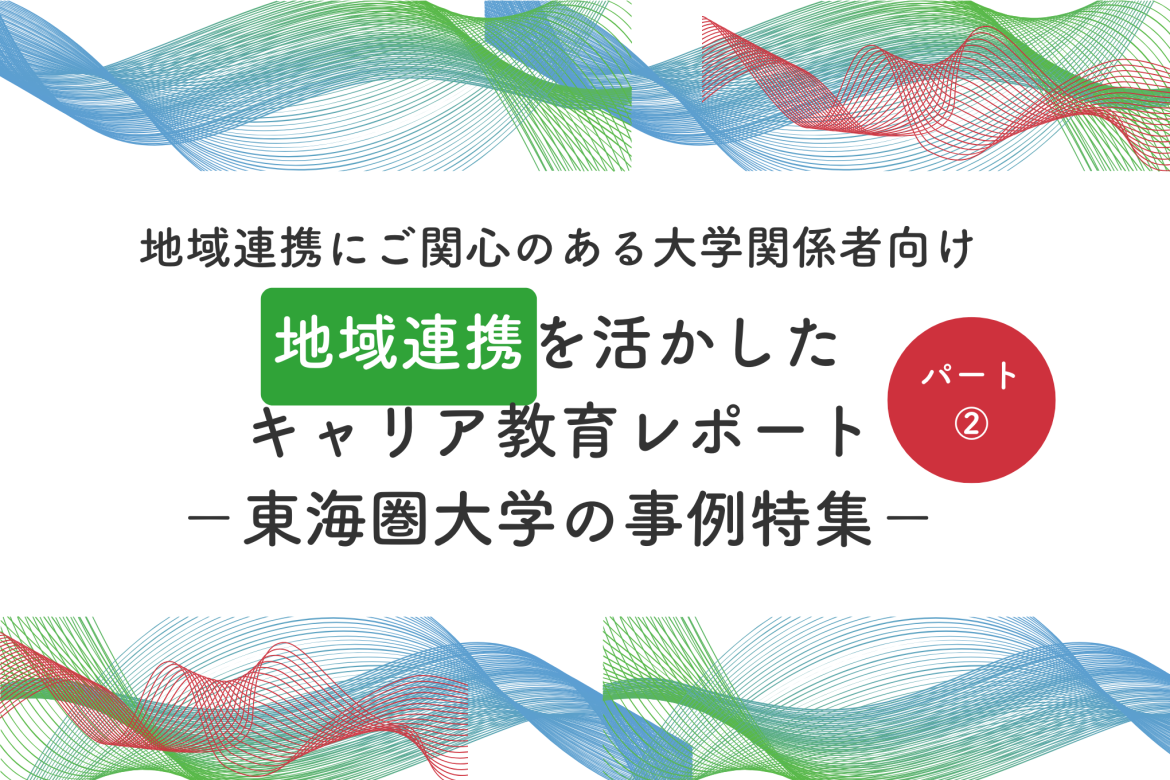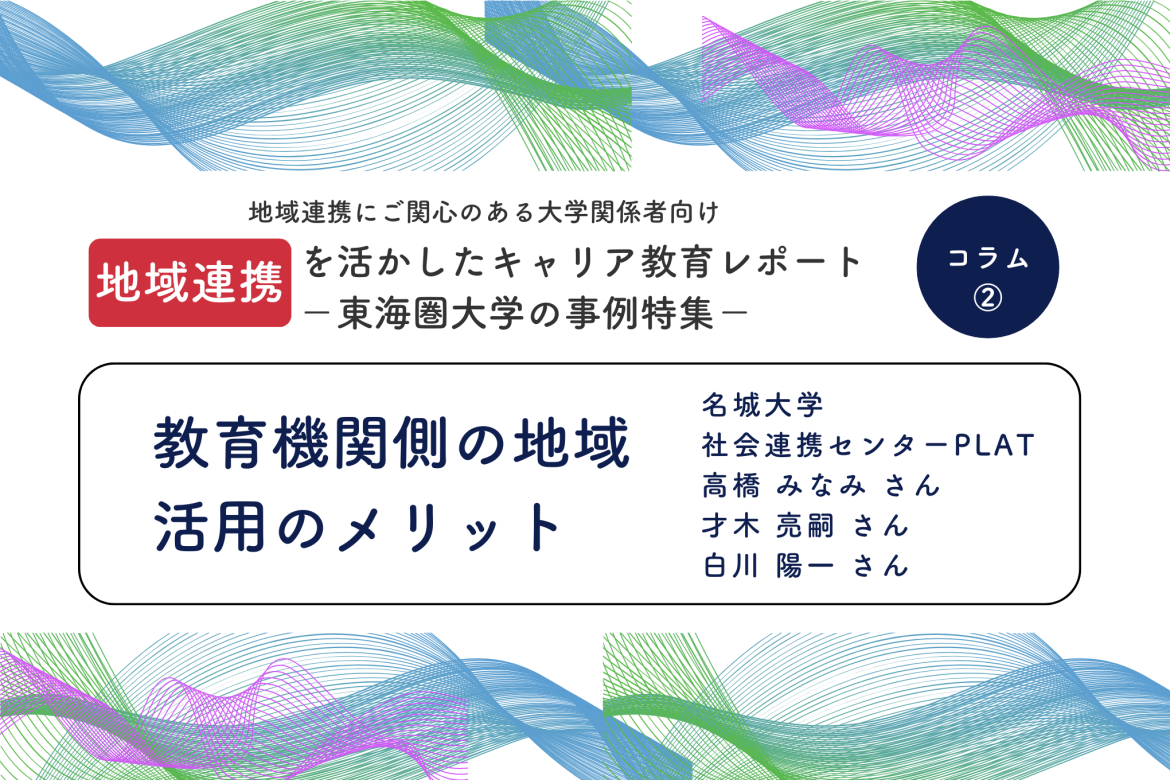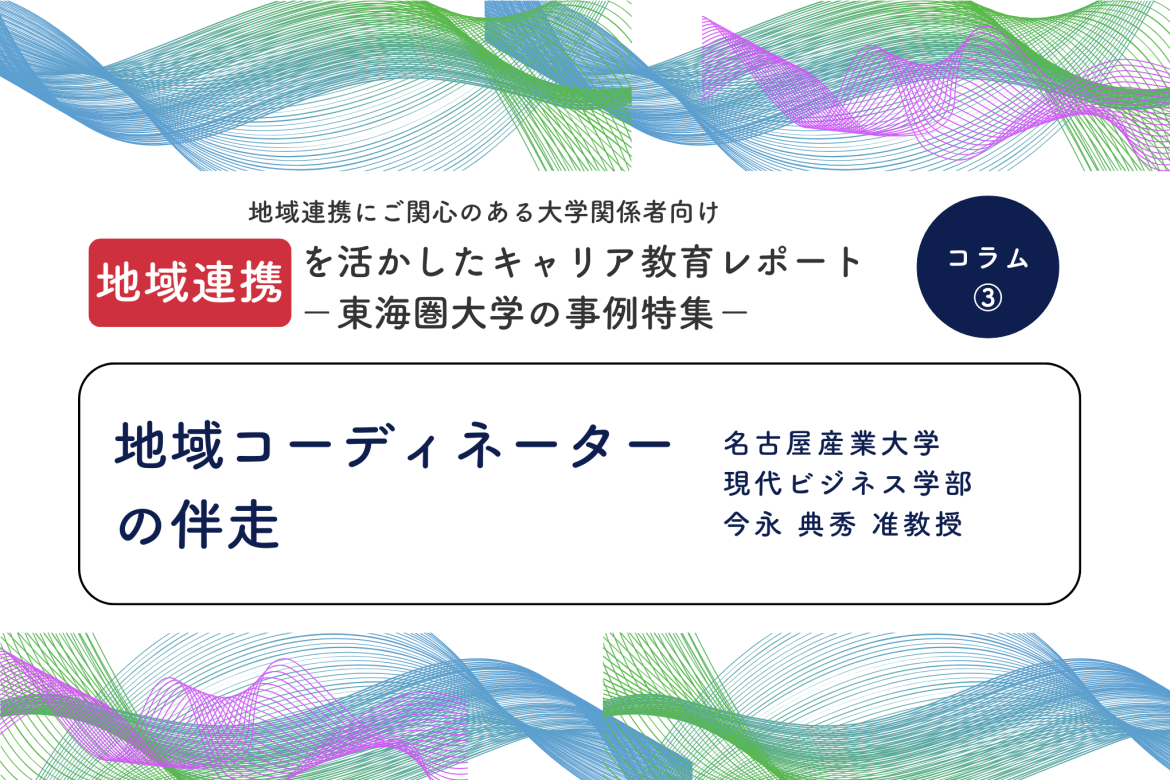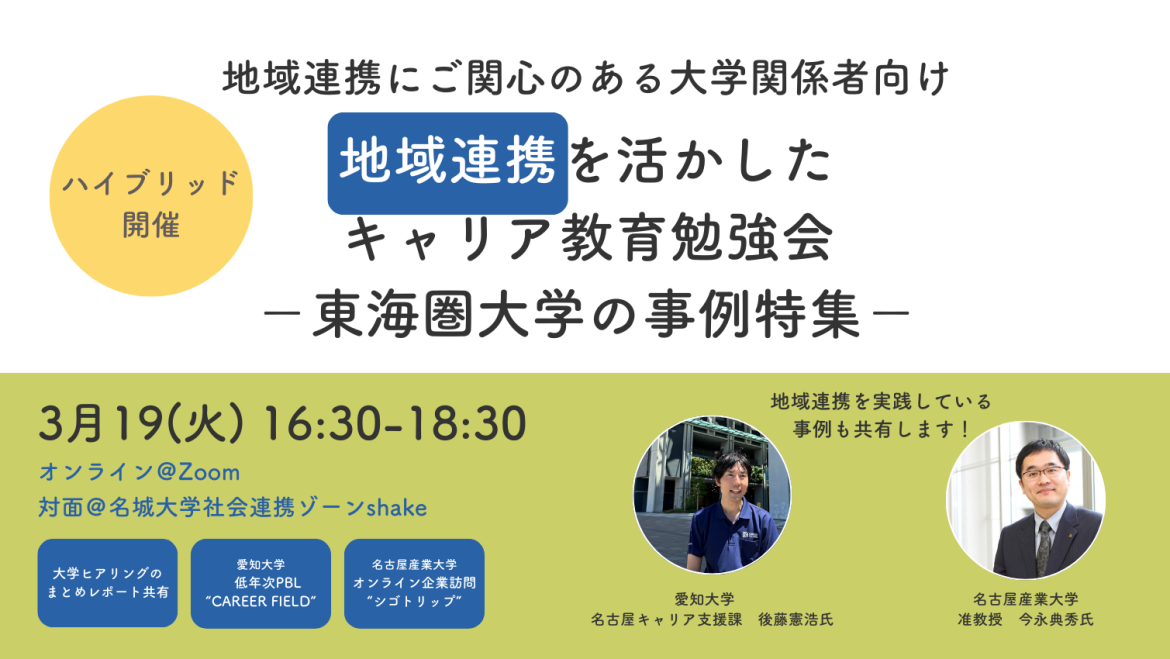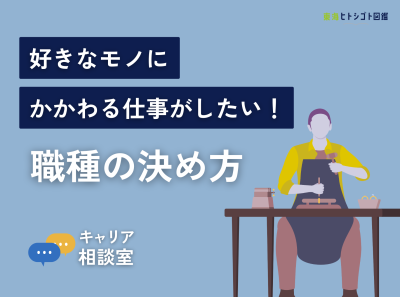2024年04月22日(月)
地域連携を活用したキャリア教育ー東海圏大学の事例集ー コラム①実践の効果、社会実装の効果
2024年04月22日(月)
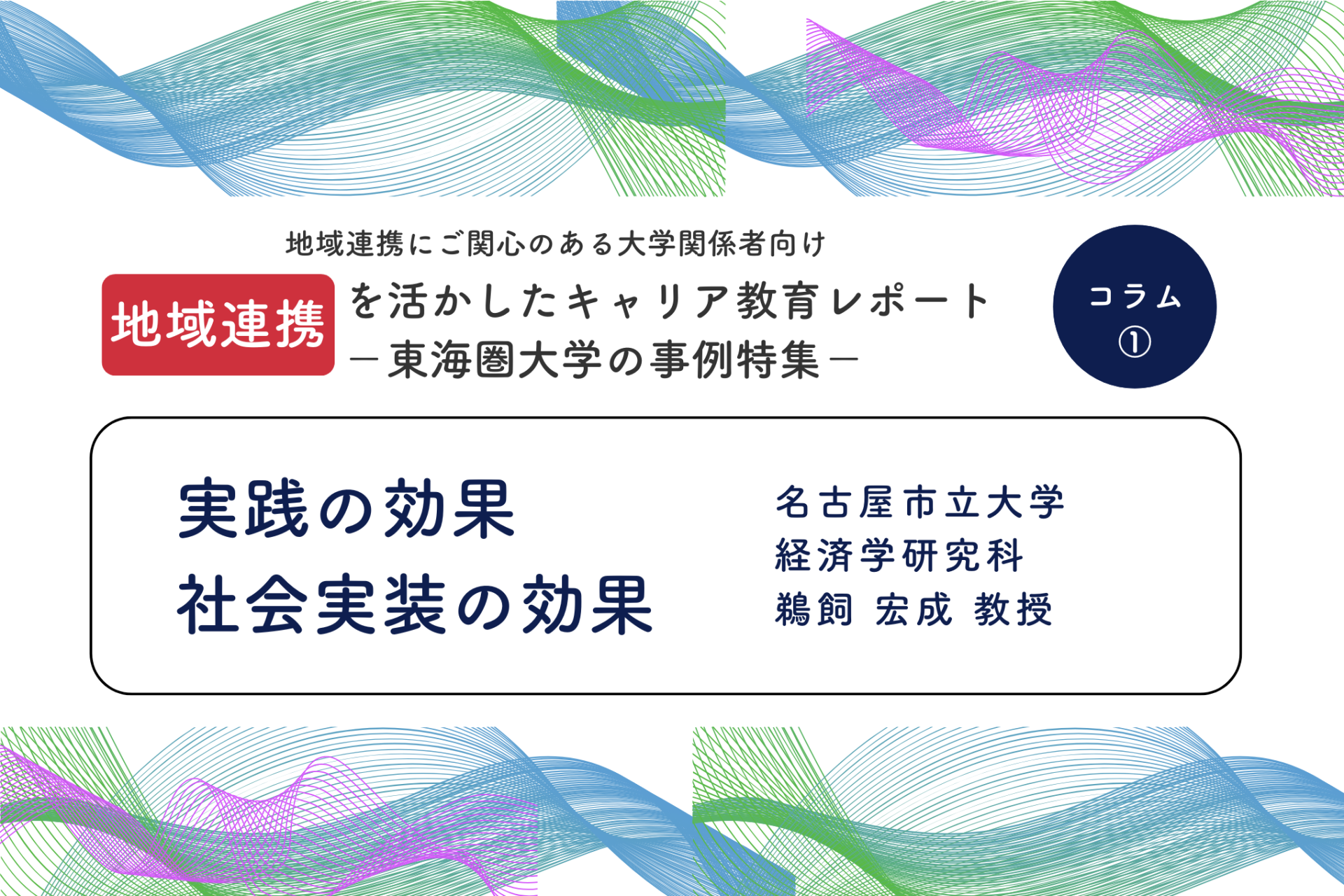
地域と連携した取り組みを積極的に行われている東海圏の教育機関の方から、地域と連携したプログラムにおける知見をインタビューしました。
| 『地域連携を活用したキャリア教育-東海圏大学の事例集-』レポート(PDF) ▼その他記事リンク |
| コラム① | 実践の効果、社会実装の効果 |
|実際の挑戦からしか学べないこと
私は企業から大学に転身した時、大学の役割を「人づくりのための育成機関」であると捉えました。座学だけでは、実際の挑戦や失敗から得られるワクワク感や試行錯誤の経験が得られません。また基礎理論だけでなく応用理論も重要ですが、応用理論は実践を通じた経験学習からしか効果的に学べない側面があります。
|実践を通した選択と決断の繰り返しから得られる課題対応能力
自分から企業に提案したことが受け入れられたり、断られたりする経験や学生だけの取り組みでは見ることのできない領域の課題に立ち向かう経験など、これらは実践によって初めて得られるものです。大きな効果の1つは、変化の激しい環境で複雑な要因が重なって発生する課題に対処する能力を養うことです。実践の中で選択と決断を繰り返すことで、問題の構造を理解し言語化できるようになります。スポーツと同様に、経験を積み重ねることでしか得られないものなのです。
|教員側のファシリテーションと振り返りを通した成長実感
実践による成長は、本人でも何ができるようになったのか変化が分かりづらいものですが、個々のプロセスや試練に立ち向かった経験を、メンタリングを通じて振り返ることで、学生は成長を実感することができます。そのためには、教員側がファシリテーターとして適切な姿勢を持っていないと成立しません。理論ありきではなく、その環境における現象から問題の構造を捉えることや、学生の成長を無視してビジネスの成果を押し付けることをしないなどの姿勢が重要です。
大学での実践は、卒業後の社会での実践にも活かされます。社会実装の考え方やプロセスを学び、これを再現性のある思考として育むことで、社会において事業を実践しやすくなります。
● 問い合わせ先
東海ヒトシゴト図鑑 教育機関窓口(担当:木村)
メールアドレス:support@hitoshigoto-zukan.jp