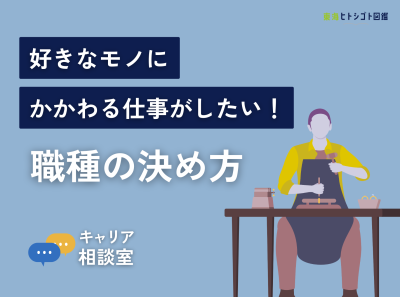2024年04月22日(月)
地域連携を活用したキャリア教育 ー東海圏の大学の事例集ー コラム③地域コーディネーターの伴走
2024年04月22日(月)
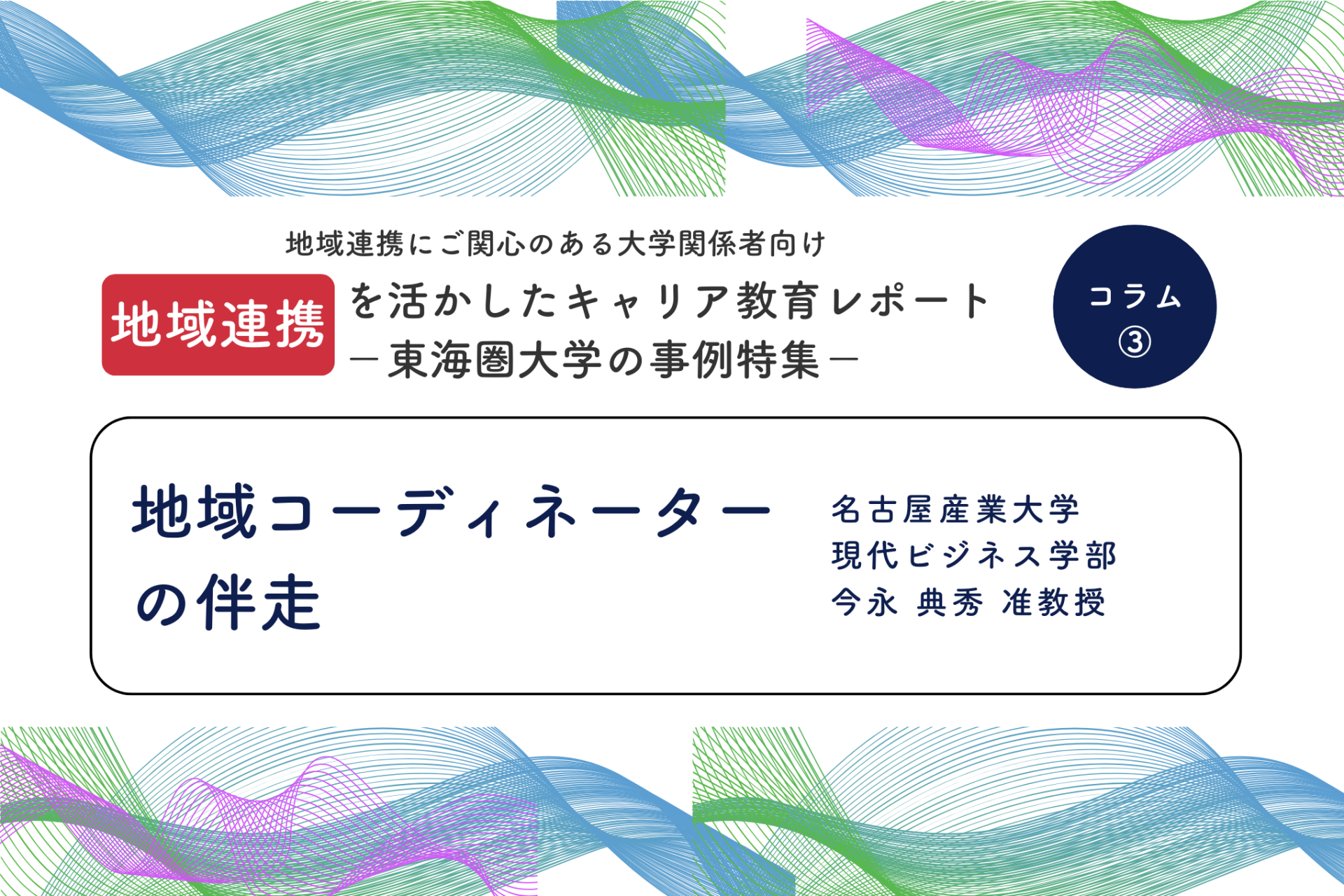
地域と連携した取り組みを積極的に行われている東海圏の教育機関の方から、地域と連携したプログラムにおける知見をインタビューしました。
| 『地域連携を活用したキャリア教育-東海圏大学の事例集-』レポート(PDF) ▼その他記事リンク |
| コラム③ | 地域コーディネーターの伴走 |
|教育機関のみでのプログラム設計の難しさ
大学と企業は異なる教育・ビジネスの立場を持っているので、大学側では教育効果が優先され、企業はやむなく大学側の意向に従うこともあれば、企業側の都合により断ることもあります。教職員のみでは企業の事情やニーズに合わせたプログラム設計が難しいことや、学内でも調整の人手が足りなかったりという問題は少なくありません。
|第三者視点を持つ「コーディネーター」を交えた設計
この問題への対策として、コーディネーターの存在が極めて重要です。企業でもなく学校でもない、異なるポジションからの第三者視点で、双方のニーズを調整するのが「コーディネーター」です。介入により様々な調整工数削減につながる効果があります。教職員が学生のサポートを担当する場合と外部コーディネーターに行ってもらう場合の違いは、学生にとって外部の人は緊張感をもちつつも相談がしやすいという点があります。
|コーディネーター活用の際の注意点
また、コーディネーターと共同でプログラムを運用する場合の注意点もあります。コーディネーターに大学の声を誤解ない様に理解をしてもらえていなかったり、大学が本来かけるべき工数が不足する場合は、教育効果が担保できません。コーディネーターに任せ切りではなく、協力と理解を基盤とした学生優先の思想が必要です。
|地域に関心を持つ人が増え、コーディネーターと学校共に成長する社会へ
今後の展望として、地域コーディネーターの増加が望まれています。経験が必要であるため、関心を持つ人を増やすことが重要な第一歩とされています。地域ごとに異なるジャンルに特化し、長期のプロジェクトにおいてはコーディネーターと学校が共に成長することが理想とされています。
● 問い合わせ先
東海ヒトシゴト図鑑 教育機関窓口(担当:木村)
メールアドレス:support@hitoshigoto-zukan.jp