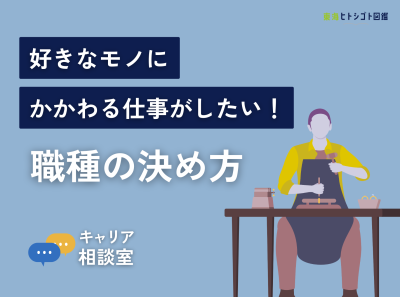2025年07月09日(水)
未来を作る町工場!ヒューマノイドと歩む革新の道
2025年07月09日(水)

■トヨタ自動車を支える試作製作所
私たちは今回、愛知県豊田市にある株式会社秋山製作所を訪問して様々なことをインタビューしました。秋山製作所は、自動車のドアやアーム(車輪の動きを制御したり、部品同士をつなぎあわせてタイヤに力を伝えたりする役割を担う)などの部品試作から金型設計製作・レーザー加工・プレス加工・組付け・量産までを一貫して手掛ける社内一貫製作を行う企業です。試作や金型製作といっても簡単にできるわけではなく、職人さんが機械を駆使し何回もトライ&エラーを繰り返し細部までこだわって作り上げています。
この企業の最大の特徴は、最新のテクノロジーと職人の熟練技術とを掛け合わせた試行錯誤を行っていること。

写真1 3次元測定機
例えば、鉄の板を湾曲させる加工の際には写真1にある機械で光の反射の仕方で鉄を測定します。鉄の測定は0.01mm単位の微細な誤差まで求められるため、大きな機械とは裏腹にとても繊細な作業です。現在のような技術を導入する前は、職人さんが手作業で鉄の厚さを測るような時間と気合がいるような作業でした。しかし、コンピューター技術の向上によりシミュレーションをすることによって時間とコストを大幅に削減することに成功したそうです。
- 写真 2 従来の測定機(正面)
- 写真 3 従来の測定機(横)
機械を実際に見学させて頂いたところ、プレス加工、ASSY工程(製造業における組み立て工程)、2Dレーザー加工(平面的で縦と横を軸に動く)・3Dレーザー加工(立体的で首を動かし、縦・横・奥行きを軸に動く)など現代の技術を最大限に活用し、機械と職人さんが向き合う姿に感銘を受けました。工場を見学する中では、工場最大のプレス機械(600t)が稼働しているところを特別に見せていただきました。プレス機が稼働するたびに大きな音と振動を感じましたが、精密な動作によって多くの部品を作成しています。
- 写真 5 2Dレーザー
- 写真 6 3Dレーザー
■AIを駆使する工場が描く未来
秋山製作所は差別化とイノベーションを目指し、2025年から「AS2030」という中期計画を進めています。この計画ではこのように人間とロボットの共存がこれからのテーマになると考えられています。AIやヒューマノイド(人間に似せて作られたロボット)技術を活用し、工場の未来像を段階的に実現していくことを目指しているそうです。

秋山製作所が描く未来
担当の方によると2026年には作業内容をAIで解析し、2027年にはその解析結果を基にAIが作業をサポートすることで、即戦力となる人材を育成。さらに2028年には作業の言語化を進め、多国籍な人材が働きやすい環境づくりを推進し、最終的に2029年にはヒューマノイドによる作業の実現を目指しています。これを実現するためには様々な課題があります。例えばAIツールの選定、人材育成、作業の言語化、外部連帯の強化、多様な人材に対応した育成体制などいくつもの課題があるようです。こうした課題に向き合いながらこのような未来工場を実現に向けて日々試行錯誤を重ねています。
■秋山製作所の見えざる組織活動
秋山製作所が大切にする価値観の一つに「社員の幸せ追求」があります。このため、秋山製作所はアットホームな職場づくりを全体の目標とし、コミュニケーションが行き交う環境を作ることで社員間の関係を深めやすくし、溝のない職場環境の実現を目指しています。また、地域密着型企業としての手本となるべく、地域貢献活動にも力を入れ、地域の方々から応援される存在となるように心がけているそうです。具体的には交通安全週間において地域住民との立哨の参加や地域の環境美化活動、小学生を対象とした夏場の下校時における補水所の提供などにも積極的に取り組んでいます。
■AIによって変わる秋山製作所
そして今後は、37人中35人が男性という職場環境の改善も検討しているそうです。今まではライン作業を手作業で行っており、重い鉄を運ぶことや汚れるといった負荷から女性の社員比率が低かったそうですが、今後はAI導入が進んでいく中で、女性の活躍も期待できます。また、地域社会の労働力を向上することを目的として、働き方改革の一環として、AIサポートを活用し、短時間で活躍できる環境を整えて、フレックスで柔軟な職場環境づくりを進めているそうです。人材の教育面でもAI関連で力を入れておりAIプログラミングが可能な人材を目指すべく、社員教育面でのサポートも充実させています。AI社会への転換が進む中で、時代に沿うために、社員にAI学校を受講させ、また役員自らがAI講習を全社員に行っているため、AIの対応はもはや社員全員が可能となるとのこと。AI活用は事業推進だけでなく、多様な人が活躍できる組織づくりにおいても重要であることが分かりました。
<企画概要>
とよた市みんなの人事部×名城大学経済学部×東海ヒトシゴト図鑑
学生が企業の“戦略”に迫る、実践的フィールドワークプログラム
本記事は名城大学経済学部の「社会フィールドワークI・II」の受講生が取材・記事執筆を行いました!
学生の視点で産業構造や事業の強みを分析し、魅力を深掘りした内容になっています。
本プログラムの関連記事は、ページ下部よりご覧ください。